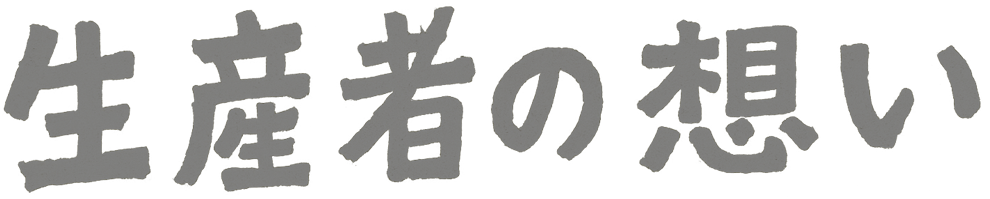
長男 原田純也

熊本・植木町で六十年、
スイカと向き合ってきました。
原田重治・陽子
種は何も語らない
(語られないうちに始まっていること)

土に蒔いたスイカの種は、
しばらく何も語らない。
動きもなく、
そこに本当に命があるのかどうか、
見ただけでは分からない。
けれど、寒い夜、
誰もいないハウスで、
必要なときだけそっと温度が守られるように、
その時点で、
スイカの種には、人の思いが静かに伝わっている。
まだ芽も出ていない。
まだ春も知らない。
それでも、
この命に託される役割は、
もう決められている。
芽が出るということ
(生まれることと、役割を持つこと)

やがて、
小さな芽が土を押し上げる。
外の世界に、
恐る恐る顔を出す。
生きている、ということが、
ようやく目に見える形になる。
ほっとする間もなく、
この芽は、
まもなく首を切られることになる。
まだ何も実らせていない。
まだ何者でもない。
それでも、人はためらわない。
畑に立ち続け、
やがて、
誰かの笑顔を運ぶために。
首を切る理由
(畑に立ち続けるための決断)

スイカは、そのままでは弱い。
病気に負け、
土に負け、
途中で倒れてしまうことがある。
だから、
強い根を持つ、かんぴょうの力を借りる。
ふたつの命をつなぎ、
春の畑に、
立ち続けられるようにするためだ。
この作業は、
いつでもできるわけではない。
小さすぎてもいけない。
大きすぎても、もう遅い。
その一瞬を逃せば、
その年のスイカは、始まらない。
刃物の角度
(ほんの一瞬にすべてが決まる)

刃物の角度は、
ほんのわずかでいい。
立ちすぎても、
寝すぎてもいけない。
指先に乗せた、
直径二ミリほどのスイカの穂。
その細い首に、
刃先をそっと当てる。
角度を誤れば、
断面は小さくなる。
それだけで、
命はつながりにくくなる。
心臓の音が、
指先まで伝わってくる。
息をひそめ、
刃は動かさず、
穂のほうを、静かに引き抜く。
手が震えれば、それで終わりだ。
ためらわずに、切り落とす。
夜の苗床
(誰にも見られない時間)


母から聞いた話がある。
私がまだ小さかった頃、
子どもたちが寝静まったあと、
夜中の十二時近くまで、
父と母は苗床のあるハウスに灯りをつけ、
この作業を続けていたという。
外は真っ暗で、
光っているのは、
ハウスの中だけ。
眠っている家族と、
これから生まれる命のあいだで、
ただ黙々と、手を動かしていた。
誰にも見られない時間に、
未来のスイカは、
静かに仕込まれていた。
正解のない判断
(天気・温度・水・毎日の選択)

畑の仕事に、
正解は書いていない。
天候も、気温も、
昨日と同じ日は、ひとつもない。
水を入れるか。
温度を下げるか。
それとも、何もしないか。
毎日、
その場で決め続けるしかない。
これら一つひとつの判断の先にあるのは、
おいしいと笑ってくれる、誰かの時間であり、
家族を養い、
この仕事を続けていく人生だ。
父の怒り
(守ろうとしていたもの)
父は、普段は温厚で、
どちらかといえば、
真面目すぎるほどの人だった。
それでも、
仕事のことになると、
ときどき猛烈に怒ることがあった。
小さかった頃の私は、
なぜそこまで向きになるのか、分からなかった。
ただ、
空気が張りつめ、
近づきにくくなるのを感じていただけだ。
大人になり、
同じように判断を重ね、
同じように迷い、
同じように時間に追われるようになって、
少しずつ分かるようになった。
あれは、怒りではなく、
生活を守ろうとする必死さだったのだ。
見えていたもの
(見えなかった幸せ)

正直に言うと、
あの頃の自分には、
父の人生がとても苦しく見えていた。
毎日、農作業。
重労働の連続。
神経を使い、イライラし、
時には怒ったり、ムキになったり。
それなのに、
遊びもない。
旅行もしない。
趣味らしい趣味もない。
「楽しみなんて、どこにあるんだろう」
そう思っていた。
喧嘩したのは、そんな時だった。
お互いに熱くなっていたし、
自分は、かなりひどいことを言ったと思う。
「そがんはりかくぐらいなら
こがんこっせんどけばいいつた!」
「休みも無し、遊びも旅行も行けん、
趣味も楽しめんでかっ」
「何のために働きよっとや!」
そして、最後にこう言った。
「俺は、
こんな不幸な人生は絶対嫌ぞ!」
あの言葉には、
苛立ちもあったし、
反発もあった。
でも今思えば、
ただ責めたかったわけじゃない。
父に、
もっと人生を楽しんでほしかった。
苦労だけで終わってほしくなかった。
自分たち家族のため“だけ”に、
人生を使い切らないでほしかった。
その時、父も熱くなっていたと思う。
少し語気を強めて、こう言った。
「おらぁね、
この仕事しよって
辛いとか、不幸とか思ったこと、
一度もなかと!」
「ただ、
農業が本当に好きで、
好きなことば、
一生懸命しよるだけたい!」
その場では、
何も言い返せなかった。
正直、
その時はまだ分からなかった。
仕事の楽しさも、
続けることの意味も。
自分には、
ただ“きつい現実”しか
見えていなかったから。
今になって思う。
父には、
自分には見えていなかったものが
見えていたんだと思う。
それは、
顔も知らない誰か。
お客様なのか、消費者なのか、
言葉は分からないけれど。
自分が育てたスイカで、
笑ってくれる人たち。
喜んでくれる人たち。
幸せな時間を過ごしてくれる家族。
その姿が、
父の中では、
ちゃんと見えていたんだと思う。
畑に立ち、
一苗に一玉だけを残す。
一苗一玉。
それは、
効率のためだけじゃない。
自分の仕事に、
最後まで責任を持つということ。
そして、
誰かの幸せを思い浮かべながら
手を動かすということ。
あの時、
自分は「こんな人生は嫌だ」と言った。
でも今は、
少しだけ分かる。
父は、
不幸な人生を生きていたんじゃない。
好きなことを、
誰よりも真剣に生きていただけだった。
背中を受け継ぐ
(父と息子、ふたりの畑)

いまも父は、
畑に立ち続けている。
体は、
もう昔のようには動かない。
それでも、
朝の空気を吸い、
畑に足を踏み入れれば、
身体は自然と動き出す。
隣には、
父の背中を見て育った息子がいる。
歩幅を合わせ、
流れを絶やさぬように。
いまの畑には、
ふたりの時間と想いが、
重なって流れている。
